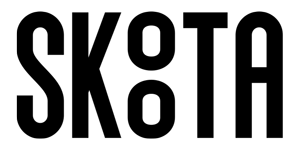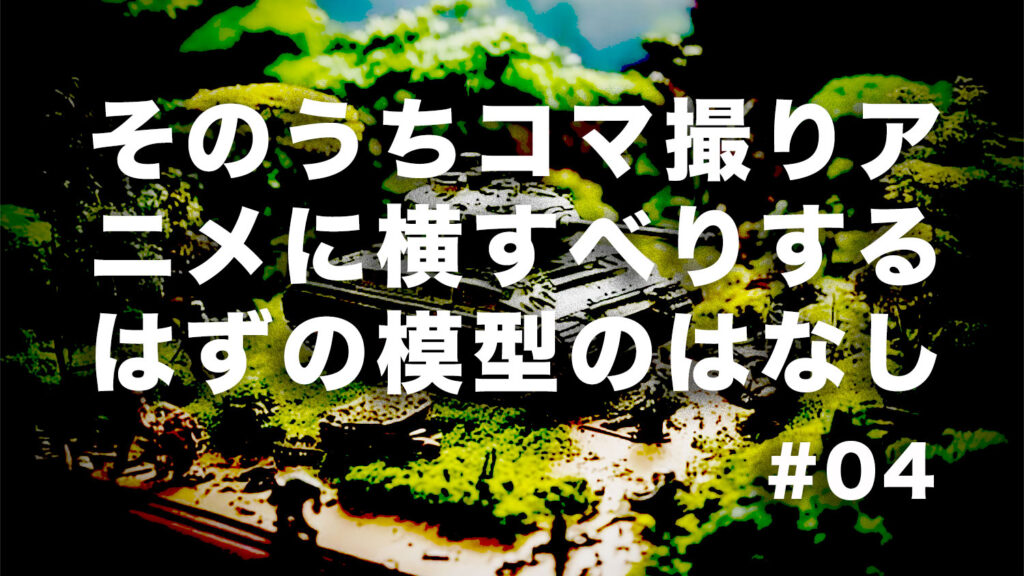模型が好き、ということを実はあまりこれまでおおっぴらに話すことは避けてきていた。 この連載の内容を考えたときも、やはりちょっと躊躇があった。模型を作る、と言うときに、それが単に模型を作るだけのホビーであると言い切れるのか、という問いかけが、常に頭の片隅に浮かんでしまうからだ。 プラモ屋にはガンダムと戦車と戦闘機と軍艦と鉄道があった 小学生の頃の話だが、近所の模型店で耳にした会話を、今でもはっきりと覚えている。 その時私は第二次世界大戦中のドイツ軍の戦車のプラモデルを探しに来ていた。探しにと言うか、見に来ていた。当時の私のお小遣いではタミヤのプラモはそんなに簡単に買えるものではないので、どちらかというと見に来ていた、と書くのが正しいのだ。 そのとき、店には何人かお客がいて(模型屋が普通に賑わっていた時代ではある!)ちょっと離れた場所で二人のおじさんが穏やかに話していた。一方のおじさんは「軍艦や戦車、戦闘機のプラモデルを作ることで、子供たちに戦争を肯定的に捉えるメンタリティが生まれてしまうのではないか」およそそんな内容の懸念を口にしていて、それに対してもう一方のおじさんが「まあまあ、プラモは単なるホビーなんだし、それはさすがに考えすぎだよ」と応えるような内容だった。模型屋にまでやってきてその二人がなんでそんな会話をしていたのか、どういう脈絡だったのかは今もって謎だが、とにかくその会話はくっきりと私の耳に残り、まさにその日、戦車のプラモを見に来ていた小学生の私は、その会話に妙な居心地の悪さを感じて、そっとその場を立ち去ったのだった。それにしてもプラモ屋にはガンダムと戦車と戦闘機と軍艦が並んでいた。あと鉄道と車とバイク。(今はフィギュアが多いよね。) そもそも模型文化が盛んな国を上げていくと、もともとは「帝国」なんてものを自認していた国々が多いみたい。例えばイギリスにおいて、鉄道模型や艦船模型が愛好されたのは、それらが誉高き大英帝国の力を象徴するアイテムだったからのように思える。かつて七つの海を支配したロイヤルネイビーの艦船を、精巧な模型として再現して愛でる — そこには単なるホビー以上の意味が込められているように思える。私の世代は、学生時代に「トレインスポッティング」を見てひゃっはーってなったりした年頃なんだけど、このいやというほど失われ果てた感じのイギリスが舞台の映画で、アル中の艦船プラモマニアの老人が出てこなかった?いやめっちゃ出てきた気がするんだけど、勘違いで全然別の映画かもしれない。とにかくアル中の老人が引きこもってぐちゃぐちゃの部屋でずっと軍艦のプラモ作ってるの。失われた栄光にすがって、自分の境遇を直視しない、痛々しい感じに見えたんだけど、これあまり人ごとに思えなかった。(うん、映画はトレスポじゃない気もする。ちょっと探してみたけど、ぜんぜんそのことに触れた情報が見つからないし。でもそれはそれとして久々に観てみたくなった。) まあ、模型にはそういう一面はあるよな気がするなぁ、と思いつつ、近年の韓国・中国の模型メーカーの躍進を見ると、かつての帝国への憧れがどうのという感慨は所詮ただの与太話のような気もしてくる。こと東アジアにおいては、「いや、なんか俺たち手先器用みたいなんすよ」くらいの方がしっくりくるのかもしれない。 そもそもこの手の問いかけは、プラモ界隈では常に非プラモの一部の人々から投げかけられる紋切り型の疑義であり、言われたくない「言いがかり」として扱われている問いでもあるだろう。その話題が出たら、もう話は終わりだ、そいつと話すことは何もない。単なる趣味なんだからそっとしておいてくれ、痛くもない腹を探られるなんてまっぴらだ。 そもそもプラモ好きは世の中でそこまで目立ってないし、街の模型屋さんは減る一方だし、むしろ絶滅危惧種じゃないかと。それはそうかもしれないと思いつつ、アンビルドの模型好きとしては、あの時の模型屋で聞いた会話は、いまだに抜けないトゲとして、どこかに刺さったままだ。 模型が教育の場でも重要な役割を果たしていたらしい、という話は、この件を考える上で無視できない。戦時中、日本の小学校(当時は国民学校ですかね、)では、木製の軍艦模型を作る授業が行われていたという。ほんとに?それで、専用の木製パーツをまとめた軍艦模型のキットが存在し、学校で一括購入していたという。委細うろ覚えなので申し訳ない限りなのだが、この話を聞いたときに思い出したのは、原爆と日本の戦争責任を正面から扱った漫画「はだしのゲン」の中で描かれる情景だ。そこでは、主人公のゲンが木製の軍艦模型を近所のおじさんからもらってくるのだが、ゲンの弟は空襲で崩れた家の下敷きになり、この模型を抱いて焼け死ぬ。この軍艦の模型に関する描写はけっこう重要なシーンなのだが、その背景に、学校で軍艦模型を作る、というような前提があったのかもしれない。ゲンもその弟も、そのよくできた軍艦模型をめちゃくちゃ欲しがるし、大喜びで遊ぶ。国民を総力戦遂行のために統合し、子供たち、とりわけ「男の子たち」を、まさに「かっこいい戦争」に「動員」していくシステムとしての軍艦の模型がそこにある。 全ての学校でやってたのか?とか、どの程度の履修率なのか?とか、どういう使い方(授業方法?)をしてたの?とか、疑問はいくらでも湧くけれど、模型を作るとき、手に取るときに、その人に湧き起こる感情というのは、「ホビーだよ」の一言で済ませられない何かがあって、だからこそそれを「教育」に利用しようという動きもあった、というのはそんなに外してない気がする。 ガンダムと戦時中の空想兵器 高校生の時にはガンダムを巡る議論にも遭遇した。「ガンダムは戦争を美化している!」と真っ向から批判する先輩の言葉は、高校生らしい正義感から来る極論の類ではあると思うのだが、当時すでに富野由悠季の反戦的な発言を聞きかじっていた私は先輩の論調に違和感を覚えつつも、メーカーがプラモデルを売るための宣伝アニメである、というロボットアニメの身も蓋も無い一面のことを思うと、戦闘シーンの魅力的な描写は確かに批判の対象となりうるとも思えた。よく言われることだが、ガンダムにおける空想兵器の開発体系(改造型とか旧型・新型はもちろん、陸専用とか水陸両用など、戦場によるバリエーション展開など)の豊富な設定資料を子どもたちが楽しむことと、戦中の子供達が、少年誌に掲載された空想超兵器の解説図解を楽しむことの間には少なからぬ類似性があるわけです。軍国少年が大喜びして眺めた空想兵器の図解は、そのまま戦後の子供雑誌が描く「未来都市の図解」につながるが、もう一つ直系の子孫がガンダムなどのロボットアニメの設定資料だったりする。 かく言う私もそういうある種のリアリティに満ち溢れた設定資料本は大好物だった。だから、戦中の少年誌に掲載された空想科学兵器の図解のことを聞くと、あー、その頃子供をやってたらやっぱり夢中になったかもなーとは思う。 別に軍艦や戦闘機のプラモを作ったからと言って軍国主義者になるわけじゃないが、模型が生み出す感情の中にしのんでいる何かしらの「種」がうっかり芽吹くようなことは未来永劫絶対に無い、とまでは言い切れないものは感じていた。やはり「かっこいい」戦闘機や戦車や軍艦のプラモ作るとなにかしら「盛り上がる」気持ちがあるのは、自分でもわかるもので。 おもちゃ遊びをする「偉い」人たち 映画化もされた三田紀房の漫画「アルキメデスの大戦」は、軍隊嫌いの天才数学青年が大和建造を止めようとして大和を設計しちゃったり、零戦を設計しちゃったりするトンデモかつ割と真面目な漫画なのだが、その中で海軍の「偉い」人たちがこれから建造する予定の軍艦の模型を並べて、きゃっきゃしながら「これがいい」「あれがいい」と言ってるのを、「おもちゃ遊び」と揶揄する発言がある。別のシーンでも、図上演習用に作られた小さな軍艦模型を見て、それを持ってやっぱりきゃっきゃする軍参謀たちが描かれる。これけっこうこの作品のテーマだとも思うんだけど、戦争は「おもちゃ遊び」と地続きな面を否定できないかもしれない。おもちゃ遊びの果てに殺したくも殺されたくもない。 ミニチュアはある意味で「神の視点」を楽しむものでもある。明治期にはすでに戦場のジオラマ再現と写真投影を組み合わせたパノラマが見せ物になっていたりしたようだが、それまで支配者が独占していた「神の視点」は大衆の時代においてしっかりとエンタメになっていく。見せ物のパノラマは、すぐに活動写真にとって変わられ、やがて特撮映画になっていくだろう。特撮映画が模型を駆使して作り出した、どこか素朴でぎこちない戦闘シーンは、今やCGによって圧倒的なリアリティを持って再現されるようになった。CGはある種、バーチャルな模型のようでもある。そして映画が語るドラマとは切り離して、再現された兵器が画面内いっぱいに映る戦闘シーンを楽しむ。その精緻で魅力的な映像は、戦時中に多くつくられた戦意高揚の宣伝映画と同様、兵器が「一番カッコよく見える」映像だったりもする。 呪具としての模型 模型はある意味で呪具なのかもしれない。それは鎮魂の器となったり、恨みの連鎖を宿したり、あるいは時として力への際限のない憧憬を育んだりする。模型自体は、何か根源的な生命力というか、呪詛の力というか、そんなものを呼び覚まし増幅する不思議な力を持っているようだ。 小学生の頃に感じた居心地の悪さは、実はこの解決し難い両義性を呼び覚ます、模型の本源的な性質への直感だったのかもしれない。 そしてそれは今も続いている。 はらだ
「2024.10月秋季回歸大戰」每月KPOP閒聊 第二季 #03
2024/11/07 今年的秋天真是火熱。這不是在說氣溫。 當然,氣溫的確也不像秋天那樣,但更讓人熱血沸騰的,正是大家所熟知的KPOP。 特別是在10月份的回歸盛宴,或稱回歸大戰,想必所有KPOP粉絲都心潮澎湃。 在這裡,將10月的主要回歸整理於下。 10月4日LISA(BLACKPINK) 10月9日KARINA,NING NING,WINTER,GISELLE(aespa個人曲) 10月11日JENNIE(BLACKPINK) 10月14日SEVENTEEN 10月15日KISS OF LIFEITZY 10月18日ROSE(BLACKPINK)&Bruno Mars 10月21日aespaILLIT 10月23日tripiesS Visionary Vision 10月28日THE BOYZ 10月30日STAYC 10月31日G-DRAGON(BIGBANG) 如你所見,這樣眾多人氣組合及其成員的個人曲在十月紛紛回歸。 在這裡,我打算特別提及三點。 首先是,BLACKPINK中有三位成員幾乎在同一時期回歸的這一點。 這種情況一般會發生嗎? 雖然BLACKPINK的粉絲團體龐大,但彼此之間卻可能會因為搶奪銷售而產生影響,因此相對於優勢,劣勢可能更大。 通常情況下,若稍微錯開時間來各自回歸,銷售上會更有利。 那麼,為什麼會發生這樣的情況呢? 因為BLACKPINK雖然作為團體與YG娛樂續約,但四名成員皆已離開YG,並各自隸屬於不同的公司。 因此,可以想像到JENNIE、LISA和ROSE都會對此感到驚訝,彼此的公司關係者也會想「如果是這樣的話,早點告訴我們啊」。 第二點是10月21日aespa與ILLIT同日回歸的事件。 這場直接對決作為現今KPOP女歌組的巔峰較量,吸引了除了兩組粉絲以外的熱烈關注。 ILLIT在今年三月發行的出道曲「Magnetic」在全球引起了極大轟動。 在韓國各大音樂排行榜上全都同時奪冠,達成了「完美全殺」的成就,並且在美國Billboard主要排行榜「HOT100」上成功進榜,成為KPOP出道曲史上的首例,隨後也連續22週進入榜單,創下了輝煌的紀錄。 作為對手的aespa也在5月發行的「Supernova」大賣。 與ILLIT一樣達成了「完美全殺」,並且在韓國主要音源排行榜Melon上連續15週奪冠,超越了NewJeans在「Ditto」中創下的14週連冠,更新了連冠最長紀錄。 而收錄了「Supernova」的專輯「Armageddon」首周銷售達115萬張,實現了四部作品連續白金銷售。 基於這些因素,第四代女歌組女王aespa與第五代女歌組女王ILLIT的對決,預期將實際成為女歌組巔峰的較量。 大家都緊盯著aespa的新曲「Whiplash」與ILLIT的新曲「Cherish(My Love)」哪一首會登上排行榜第一名。 而第三點引人注目的則是,這場秋季回歸大戰的勝者究竟會是誰? 但結果卻並不是aespa也不是ILLIT。 那麼,究竟是誰呢? 居然是…ROSE。 BLACKPINK的ROSE(雖然才27歲,但是依然算年輕)與Bruno Mars合作的歌曲「APT.」如今正席捲世界音樂舞台。 這首歌的受歡迎程度已經超越了KPOP的界限,幾乎可以說全世界都在為「APT.」而瘋狂。 音樂視頻在公開兩週內已突破2.6億的播放次數,在韓國也達成了「完美全殺」。
たろちん的旅程 編輯後記
たろちん和しおひがり的錄音中,講述了兩人伴隨著友情走過的人生變遷,交織著他們樸實的幽默感和真摯的思考。透過たろちん所經歷的「網路世代」獨特成長過程,以及對自我表達的探索和聚焦,浮現出たろちん獨有的「青春」,我打算在錄音後進一步深入探討。 たろちん的青春時代與自我探索 1985年出生的たろちん,成長於日本經歷泡沫崩潰後的經濟困難,同時也是網路迅速普及的時代。他的世代被稱為「數位原住民」,是第一個從小就與網路親密接觸的世代。他在中學時期接觸到網路,隨後開始創建「文本網站」,作為自我表達的場所,開始在網路上發聲。儘管對學校教育持懷疑態度,並對社會框架感到反感,但家庭中父母的支持「做你想做的事」給了他探索自我的自由。 たろちん和しおひがり經常提到的「小ひろゆき」這個詞,反映了當時網路論壇和部落格文化的興起,網路的匿名性使得發表意見變得容易,刺激了年輕人的自我意識。這裡可以看到たろちん提出的「義務教育是誰決定的」的問題。他被推動著超越學校的框架進行自我探索,對知識的好奇心和選擇自己道路的勇氣,顯然是通過網路萌芽的。 與網路共同成長的たろちん たろちん在2008年左右開始在Niconico動畫上進行遊戲實況。當時,視頻直播平台正處於萌芽期,實況主們彼此之間保持著緩和的聯繫,形成了一種「同世代」的社群。他所憧憬的「優待組」的實況主しんすけ的存在,對他來說也是一個巨大的刺激,通過實況活動逐漸建立起自己的歸屬感。在這個實況主數量仍然不多的時代,實況夥伴們經常聚在一起,交流的機會也很多。這樣的早期Niconico動畫文化可以說是他所經歷的「數位青春」。此外,從中他與知名實況主建立聯繫,獲得作為作家的工作機會也非常有趣。 當時的Niconico動畫被許多年輕人視為「自我發聲的場所」,在社群中互相激勵,形成了在網路上探索「自我」的時代。這樣的網路成長,補充了他在20多歲時所感受到的「現實的不確定性」,成為他個性和內心的重要支撐。 與しおひがり的友情與「知曉悲傷」的20代 たろちん和しおひがり的友情中,感受到彼此在困難時期互相支持的「摯友」之情。特別是たろちん所說的「20代,知曉悲傷,徘徊於街頭」的表達,充滿了他們共同克服社會上孤獨和不安的記憶。兩人每週聚會幾次,喝酒,分享日常的煩惱和現實的鬱悶,互相支持。實際上,たろちん回顧那段時期時提到「在街上徘徊」,對於他來說,無法在現實中找到「穩定」,友情成為他心靈的一個支撐。 之後,たろちん進入了ねとらぼ的編輯工作,而しおひがり則開始作為自由插畫家取得成功,兩人的關係也隨之變化。雖然他們在聚會時仍然會說「再做些有趣的事」,但實際上卻很難實現。然而,當たろちん再次回到自由職業者的身份,作為「期待已久的無職」與親密的朋友一起挑戰有趣的事情時,讓人感受到他正在以自己的步調逐漸找回「自我」。 人生的轉機與「エレファントカシマシ」的支撐 たろちん的人生中,特別令人印象深刻的是他受到エレファントカシマシ的「俺たちの明日」這首歌曲的支撐。這首歌表達了「10代、20代、30代的悲傷與愛」,對他來說如同一首激勵自我的「人生主題曲」。エレファントカシマシ的主唱宮本浩次在歌詞中講述的生活的悲喜交加,恰如其分地代言了たろちん的經歷,深深刻印在他的心中。 在這首歌中,10代的「對社會的反抗」、20代的「悲傷」、30代的「責任與愛」等情感得以重新確認,成為他「肯定自我的音樂」。エレファントカシマシ的音樂超越了單純的娛樂,成為他人生的指引,並作為內心強大生活的支撐。 最終,たろちん的人生是一條不斷探索「自我為何」的道路,接受失敗和變化,重生的過程令人印象深刻。他被迫戒酒的情況中,顯示出他離開飲酒這種「逃避」,重新審視自我的決心。通過疾病尋找新道路的他,正經歷著人生中「戒酒」這一結束,並試圖再次站立在自己的雙腳上,未來的活動令人期待。 網路中的「陽光角色模仿」與自我表達 接下來,我想從他們的對話中提到的「文本網站」和「USTREAM」等個人發信媒體入手,談談網路在某種程度上呈現出「村社會」的樣貌。從1990年代末到2000年代初,網路雖然廣泛普及,但仍然是一個封閉的空間,許多用戶集中在有限的層面。因此,網路上的自我表達自然形成了擁有相似價值觀的群體,彼此之間發展成為一個高素養的「村」。在這裡,個人的人性和嗜好得到了強烈的反映,文本和早期的遊戲實況等簡單而個人的內容成為中心。 在たろちん和しおひがり的對話中,他們的自我認知中隨處可見「陰暗角色模仿陽光角色」的情況。在他們的時代,網路常常被視為社會的「陰暗面」,而在這樣的環境中探索自我表達的他們,帶入了部室文化和朋友之間的內部氛圍。然而,這不僅僅是模仿,對他們來說也是確立獨特身份的過程。在脫離物理空間的網路上,「想要表達喜愛的事物」的衝動得以具體化,並最終連結到後來的YouTuber、Vtuber和實況主文化。 此外,「合作」這一概念在當時也常常被避開,這也象徵著當時網路的氛圍。作為個人表達的場所,尊重他人不干涉的原則,但在當前的網路中,卻以集體活動和與大量追隨者的互動為前提。從重視隱私和個人性文化的轉變,明顯地過渡到追求合作和大眾性的時代。 網路的開放與地下性消失 他們提到的「智能手機的出現使網路變得混亂」的話,突顯了封閉的網路空間因擴展而多樣化的變化。隨著社交媒體的普及,網路向大眾開放,從「陰暗角色的領域」變成「陽光角色也參與的場所」。這一變化使得曾經明確的群體之間的界限變得模糊,僅僅成為「普通的網路」的屬性,這使得曾經的網路用戶感到疏離。他們的言語中流露出對於網路曾經是部分人群的「地下表達場所」的懷念。 たろちん和しおひがり將自己定位為「網路老人」,並談論對過去的懷舊。他們所培養的「網路生活方式」,在現代大眾化的網路中似乎逐漸失去立足之地,這種孤獨感也隨之表現出來。 「心靈遮斷的觸發器」與「未曾改變的自我」 經歷生死的邊緣,たろちん持續面對價值觀,從他身上流露出對生命的思考,或是失去後才意識到的事物,以及日常生活的重要性,然而在克服生命危機的同時,他的死生觀卻並未有太大改變,這一發現為他的言語增添了獨特的深度。以下將詳細記述。 たろちん提到,酒精對他來說不僅僅是嗜好品,而是「心靈遮斷的觸發器」。他依賴酒精來斷開日常的焦慮和思考的連鎖,但這一切因病而中斷。經歷了死亡危機並成功生還後,曾經理所當然的酒卻突然「消失」,使他的心陷入空虛的狀態。他形容自己「變得空洞」,這種失落感或許成為他意識到「重新定義自我」的契機。 另一方面,他所說的「未曾改變的自我」也令人印象深刻。一般來說,人們在面對生死邊緣的經歷中,期待著「人生觀的改變」。然而,他卻斷言「什麼都沒有改變」。他解釋說,死生觀和人生觀並未有太大改變,這本身就是「人性的本質」,這一觀點與常見的社會觀念形成鮮明對比。 此外,たろちん在表達重新出發作為自由職業者的決心中,他面對不安的方式也引人注目。自由職業者容易失去經濟上的安全感和生活的穩定,生活方式常常伴隨著風險。他在感受到這種不安的同時,卻也在追求工作上的決心與自由和自我實現之間尋求平衡。他將這視為「因失去胰臟而獲得的新生活方式」。 另一方面,しおひがり則堅持徹底直視不安的生活方式,這有時使他變得精神上強大,但也可能成為他的一大負擔。 整個錄音的總結是,たろちん在經歷了生死邊緣的經驗後,雖然說「什麼都沒有改變」,但實際上卻在「重新確認自身立場」的過程中獲得了新的覺悟。這一再發現或許是他新旅程的開始,並將成為未來發展的基礎。 (撰寫:迫田祐樹)