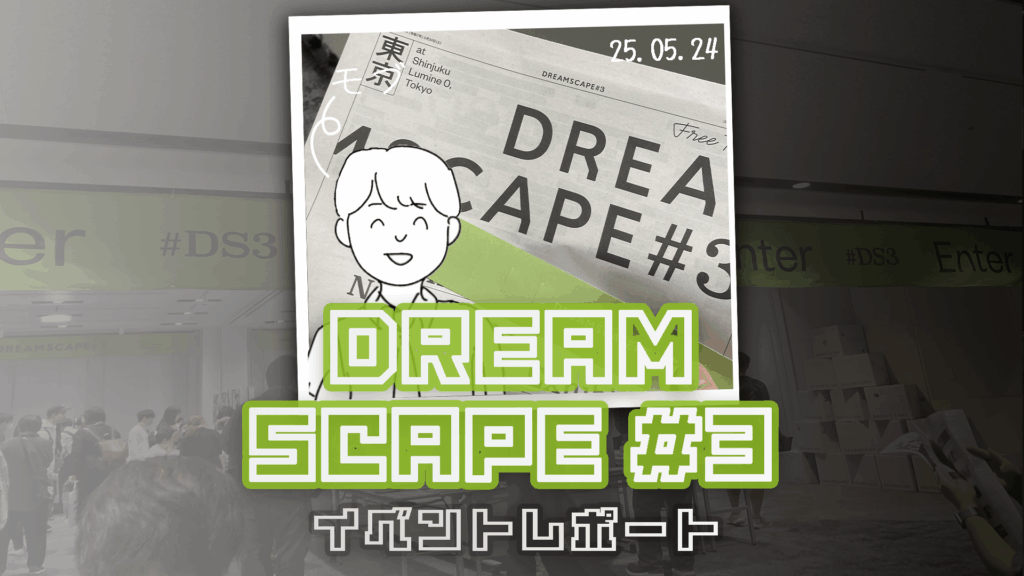あけましておめでとうございます。 SKOOTAGAMESのネゴラブチームに所属しております、モブです。 新しい年、2026年が幕を開けましたね。皆様、どのようなお正月を過ごされたでしょうか。 私はというと、少し時計の針を戻しまして…昨年の暮れ、12月27日、西の都・大阪へと向かっておりました。 その目的はただ一つ。2025年最後にして、関西初上陸となるインディーゲームの祭典、「大阪ゲームダンジョン」をこの目で確かめるためです。 師走の忙しさもピークを過ぎた時期でしたが、会場となった大阪・梅田のスカイビルには、寒さを吹き飛ばすような熱気が渦巻いていました。東京で生まれた「ゲームダンジョン」が、ついに大阪の地でどのような化学反応を起こすのか。 会場を巡りながら私が感じたのは、ここに集まったゲームたちの持つ、ある種の「個性」と「潔さ」でした。 万人に好かれようと角を削るのではなく、尖った部分をあえて残すことで、唯一無二の面白さを追求する姿勢。それは人によって好き嫌いが現れる箇所になるかもしれません。しかし、だからこそ波長が合った時には、代わりの効かない「最高のゲーム」になり得るのです。 今回は、そんな少し癖はあるけれど、だからこそ私の心に強く響いた四つのゲームについて、私が感じた「好き」の理由と共にお届けしたいと思います。 ぜひ、あなた自身の「好き」を探すつもりで、読み進めてみてください。 DRAW WORLD:「ババ抜き」ではなく「ハリガリ」? リアルタイムで描く緊張のカードバトル まず最初にご紹介するのは、『DRAW WORLD』です。 一見すると、懐かしのRPGツクールで作られたような、マップを探索して敵とエンカウントする王道RPGのスタイル。しかし、その戦闘システムには「カードゲーム」の要素、それもデッキ構築型のシステムが組み込まれています。 コストを消費して攻撃や防御のカードを切り、敵の体力と自分の状況を見極めながら最善の一手を打つ。ここまでの説明であれば、多くのゲーマーの脳裏には『Slay the Spire』のような類似作品が思い浮かぶことでしょう。 しかし、この『DRAW WORLD』には、それらの作品とは決定的に異なる点がありました。それは、戦闘が「ターン制」ではなく、常に時間が流れる「リアルタイム」で進行するという点です。 既存のデッキ構築型ゲームが、じっくりと長考し、最適解を導き出す「ババ抜き(Joker抜き)」のような静的な駆け引きだとするならば、このゲームは反射神経と瞬時の判断力が問われる「ハリガリ」のような、動的な緊張感とスピード感に満ちているのです。常に迫りくる敵の攻撃を前に、カードを切る手には自然と力が入り、強烈なプレッシャーを感じることになります。 正直なところ、このシステムは好みが分かれる部分かもしれません。ターン制特有の「時間に縛られない安心感」や「無限の可能性を考慮できる思考の深さ」こそが、このジャンルが多くの支持を集めた要因の一つでもあるからです。 しかし、だからこそこのゲームに面白みを感じるユーザーもたくさんいるはず。「全員が好きなターン制」ではなく、「このヒリヒリする緊張感がたまらない」という誰かにとっては、言葉の通りたまらない体験になるはずです。既存の文法に囚われず、リアルタイムならではの緊迫感をカードバトルに持ち込んだ本作。そのスリルを愛するプレイヤーにとって、代わりの効かない最高の体験になる予感を感じました。 なお、『DRAW WORLD』は現在Steamで体験版が配信中とのこと。もしあなたが、思考の瞬発力を試される新しいカードバトルの形に興味があるなら、ぜひ一度プレイしてみることをお勧めします。 PLATONICA SPACE:足場のない空間で、ただ「不安」と浮遊する 続いて紹介するのは、3Dアドベンチャーゲーム『PLATONICA SPACE』です。 このタイトルにピンと来なくとも、Kazuhide Okaさんの名前、あるいはKazuhide Okaさんの手掛けた『ナツノカナタ』や『ガールズメイドプディング』といった作品をご存じの方は多いのではないでしょうか。もしそうでなくとも、会場でこのゲームが放っていた独特の静謐な空気に、思わず足を止めた方も少なくないはずです。 ゲームは、どこまでも部屋が続いているかのような不思議な空間で、宇宙服を着た一人の少女と出会うところから始まります。記憶を失っているらしい主人公(私)は、部屋を彷徨いながらアイテムを見つけ、それを配置することで少しずつ記憶を取り戻していく…というのが、主な流れのようです。 短い試遊時間でしたが、デモをプレイして私が感じたのは、「足場のない空間で、頼りなく浮遊しているような感覚」でした。 なぜこんな場所にいるのか、目の前の少女は何者なのか、自分は誰なのか。何もかもが分からない未知の空間で、「記憶を取り戻す」という唯一の手掛かりだけを頼りに、あるかどうかも分からない正解を探して歩を進める。その経験は、人によっては「ただただ不安だ」と感じるものかもしれません。 しかし、もしこのゲームに強く惹かれるとしたら、その不安でぎこちない初動の中に、「何が出てくるか分からない」という一抹の期待と、想像の余地を残してくれているゲーム内の「余白」にこそ、魅力を感じているからではないでしょうか。 全てを説明し、手取り足取り導いてくれるゲームが溢れる中で、プレイヤーに解釈を委ねる。そんな体験だからこそ、波長が合った時には深く心に刻まれるのです。このゲームは、そんな「よく分からないけれど、ずっと頭の片隅に残り続ける」不思議な余韻を愛する人々のために作られたようだと、私は思いました。 Cinch Bridge:無表情なカエルの進撃と、愛すべき「キャラゲー」の側面 三つ目に紹介するのは、2Dプラットフォーマーゲーム『Cinch Bridge』です。 プレイヤーは、自動で前進し続けるカエルの主人公が無事にゴールへ辿り着けるよう、足場となる橋やオブジェクトを配置してサポートします。落下や敵との衝突を防ぎながらゴールを目指す、一見すると非常に分かりやすく、直感的なシステムのゲームです。 しかし、その親しみやすい見た目とは裏腹に、難易度はかなり高めでした。 単に穴に落ちないよう橋を架けるだけかと思いきや、ステージが進むにつれて「焚き火を拾って蜘蛛の巣を燃やす」「剣を拾って敵を倒す」といった多彩なギミックが次々と登場し、その処理手順やタイミングを瞬時に判断しなければなりません。正直なところ、パズルがあまり得意ではない私は、その急激なテンポの変化になかなかついていけず、かなり苦戦していました。見た目から感じるハードルが低い分、もう少し段階的なレベルがあれば…という惜しさも少しながら感じました。 ですが、そんな苦戦の中でも、私がこのゲームに強く惹かれた点があります。それは、キャラクターに対する「愛着」です。 主人公のカエルは、基本的に無表情のままひたすら前進するだけです(障害物に当たれば振り向いたりはしますが)。しかし、どんな状況でも無表情を貫くそのシュールな姿や、一生懸命前に進むために動く小さな手足のアニメーションを見ていると、不思議と「頑張れ!」と応援したくなってしまうものです。 インディーゲーム開発において、リソースは常に有限です。多くの作品が「斬新なゲーム性」や「優れたストーリー」といった強みを尖らせる方向にリソースを割く中で、本作のようにシンプルながらも「キャラクターの魅力」をしっかりと感じさせる作品は、意外と珍しいのでないでしょうか。 誰もが簡単にクリアできるようなゲームではないかもしれませんが、何度も失敗しながらも、この無表情なカエルをゴールまで導いてあげたいと思わせる不思議な愛嬌。それこそが、このゲームで自ら感じる魅力であり、特定のプレイヤーを虜にする理由なのだと感じました。 『Cinch
在新宿相遇的“閱讀”遊戲們―DREAMSCAPE#3濃厚報告
大家好,我是SKOOTAGAMES的Negolove團隊成員,Mob。在敲擊鍵盤的間隙,慢慢享受沖泡咖啡的香氣已經成為我的日常。 最近,我前往了在新宿Lumine Zero舉辦的專門針對小說遊戲的獨立遊戲展覽「DREAMSCAPE#3」。這是一個專注於「閱讀」的遊戲聚集的活動,雖然相當小眾,但正因如此充滿了深刻的魅力。會場被熱愛故事的創作者和玩家的靜謐熱情所包圍。 在這次報告中,我想介紹在DREAMSCAPE#3中遇到的三款特別吸引我的個性化小說遊戲。雖然統稱為「小說遊戲」,但其表現方式和主題各不相同。讓我帶你們來認識那些讓人無法停止翻頁的作品。 今天一定要_不醉倒_絕對不會!:宅飲的夜晚,酒杯那邊搖曳的“友情”和“真心” 首先介紹的是由街八ちよ創作的『今天一定要_不醉倒_絕對不會!』這部作品。光是從標題來看,就讓人感到一種似曾相識的親切感(苦笑),這是一部讓人感到親近的作品。 故事的主角是20歲的大學生「有馬」君。他與朋友辰巳君在家中喝酒,調整酒量,目標是在不醉倒的情況下持續對話,這是一款相當具有隨機性風格的冒險遊戲。可愛的像素風格角色與此相對的是,若不小心喝多了就會立即遊戲結束,必須從頭開始,這稍微嚴苛的難度反而激發了「這次一定要成功!」的挑戰意欲。 官方網站上也有提到,本作包含所謂的BL元素。不過,像我這樣對此不太了解的人來看,角色之間的互動依然讓人感到愉快,作為清新的青春一幕來享受。然而,這並不是本作的全部魅力。角色們在不經意的瞬間所展現的舉止和台詞,正因為有BL這一元素,才會引發「接下來會發生什麼呢…?」的想像力,讓人感受到故事的深度,展現出微妙的平衡感。 令人驚訝的是,這款『今天一定不會醉倒!』目前在「小說收藏」中免費公開。每次遊玩約5分鐘的輕鬆體驗,卻有三種結局可供達成,且每種結局的條件都值得思考,讓人感覺這款遊戲的製作相當扎實,完全不輸於付費作品。角色們細緻的像素動畫,越看越讓人產生親切感。 每當在活動中接觸到各種遊戲時,我總是會想,「僅僅是有趣的遊戲」與「讓人想要分享的遊戲」之間,似乎有些相似卻又略有不同。本作正是後者,玩家們從角色們的隨意一句話或行為中讀取不同的情感,並想要與他人分享…這樣的作品讓我感受到了一種「空間」。根據開發者街八千代的說法,未來的新作也將免費公開。如果您在閱讀這篇文章時感到一絲興趣,不妨試著陪伴有馬君和辰巳君一起宅飲看看。 柘榴團地:日常中潛藏的“規則”與監視器後的不安視線 接下來要介紹的是,由きじなご製作的一人稱視角恐怖冒險『柘榴團地』。在某個街道上貼著的「團地公寓日班警衛招聘中」的告示,以及隨之而來的幾條奇怪的「規則」。光是這些,您就能明白了嗎?是的,這是一部濃厚帶有所謂「拿坡里坦怪談」風格的作品。 玩家因某種原因需要在「柘榴團地」擔任日班警衛工作10天。主要工作是監視室的監視器檢查、接待來客,以及在團地內巡邏。然而,這裡存在著幾條必須遵守的規則。「必須向住戶打招呼」「來客必須在來客名單上寫下真實姓名」……還有,「絕對不可以對穿白衣的女性搭話」。如果違反這些規則,將會有難以用言語形容的危險降臨,似乎會失去過去的平靜日常……這種暗示讓人感受到這是一部相當出色的拿坡里坦作品。 遊戲的操作方式是點擊式,非常簡單。然而,與其簡單性相反,整個畫面以黑色和紅色為基調的穩重色調、可愛的角色設計與不協調的實景背景的組合,持續給予玩家一種無法言喻的不安感和「似乎會發生不好的事情」的壓迫感。監視器的顆粒感影像、偶爾驚嚇的聲音、住戶們意味深長的話語……逐漸地,玩家感受到的精神壓迫感,正是優質恐怖體驗的真實寫照。 在這其中,我特別感興趣的是這個「似曾相識的感覺(既視感)」的存在。警備室的監視器確認訪客並與名單對照的系統,會讓許多玩家想起那部著名的《那不是我的鄰居》,而透過監視器察覺異變的元素則讓人聯想到《五夜驚魂》系列。試玩後,我有機會與開發者稍作交談,聽到他本人提到受到這些作品的影響,讓我感到驚訝。 這種「影響」若不加掩飾,反而以尊重的方式昇華,並在此基礎上構建出獨特的世界觀和故事,讓我感受到製作者的認真,以及「想要創作遊戲」的強烈熱情。令人驚訝的是,製作者開始製作遊戲的時間不久,竟然是自學到這個程度。對於他的推進力,以及將現有有趣元素以自己的方式解釋和重構的敏銳度,我只能感到佩服。因此,僅僅因為「這款遊戲與那款相似」的先入為主的觀念來評價本作,實在是非常可惜。如果有機會在某處看到,真心希望你能親自體驗一下《石榴公寓》的日常。 Day Day Neon Tea:第四面牆的另一邊,珍珠奶茶連結的“體驗” 那麼,在此次的DREAMSCAPE#3報告中最後介紹的是,npckc製作的『Day Day Neon Tea』。這是一款以近未來為背景,為機器人和安卓人提供珍珠奶茶的獨特概念科幻小說遊戲。試玩時間約為5分鐘,雖然時間短暫,但在這短短的時間內,濃縮了令人難忘的強烈“體驗”。 遊戲開始後,玩家會被“機器人規制委員會”的工作機器人提出幾個像心理測試般的問題。隨著回答問題,故事逐漸展開,但不久後,該工作機器人會說“我稍微離開一下”,然後從畫面中消失。在這裡會讓人想“咦?”但真正的驚喜在後面等著。 其實這款遊戲的試玩台上放著一張小冊子。隨意拿起來翻過來一看,上面用手寫風格的字體寫著“不要相信委員會!!如果工作人員離開,畫面變成螢幕保護程式,請點擊畫面的左上角!讀完後再翻回來!”的震撼信息…。按照指示點擊畫面的左上角後,出現了一個完全不同的隱藏畫面,故事開始朝著意想不到的方向發展。這正是打破遊戲世界與現實交錯的“第四面牆”的演出。這個設計讓人感到“原來如此”的讚嘆。 老實說,這『Day Day Neon Tea』的試玩體驗,可能很難直接想像成PC或主機遊戲的完成形態。正因如此,這個名為「DREAMSCAPE#3」的活動,正是那個地方、那一瞬間,才能夠發揮出最大光彩,這是一個極具實驗性和概念性的作品。 然而,正因如此,這次的遊戲體驗深深刻印在我的記憶中。試玩後,我看到製作者和其他玩家愉快地交流遊戲感想,讓我突然想到,也許這款遊戲的真正目的,不僅僅是單方面提供一個完整的故事,而是在這個活動的場域中,透過遊戲這個媒介,讓人與人之間建立聯繫,分享驚喜與樂趣,這種「體驗」本身才是設計的重點。 npckc過去也發表了許多個性化的作品,每一部都不受限於既有的類型或框架,自由發想。這次的『Day Day Neon Tea』雖然借用了小說遊戲的形式,但其實質可能更接近於「體驗型藝術」。如果因為「這是專屬於小說遊戲的活動」而錯過了DREAMSCAPE#3的參加者,我希望你們能知道,這裡有如此刺激且顛覆固定觀念的作品。 在DREAMSCAPE中接收到的故事“接力棒” 那麼,我們介紹了三款個性化的「閱讀」遊戲,您覺得怎麼樣呢?描繪宅飲夜晚中潛藏的人際關係微妙之處的『今天一定不會醉倒!』。描繪日常中潛藏的規則與監視恐懼的『石榴公寓』。以及,跨越第四面牆,將現實與虛構連結的『Day Day Neon Tea』。 “` 這些作品共同讓我感受到的,是它們不僅僅是「有趣的故事」,還對玩家提出了某種問題,讓人思考,並且想要與他人分享這些體驗的「空間」和「熱情」。特別是「DREAMSCAPE」這個專注於小說遊戲的活動,創作者們或許更容易挑戰更深刻、更個人化的主題和實驗性的表達。 會場雖然沒有大聲的歡呼或華麗的演出,但每個展位上,開發者們熱情地講述著他們作品中的情感,而玩家們則以認真的目光沉浸在那個故事世界中……這是一個靜謐卻充滿確實熱情的空間。可以說,這是一幅讓人重新認識故事本質力量的美好景象。 此次的DREAMSCAPE#3,對我來說,再次提供了思考「故事是什麼」和「在遊戲中講述故事的可能性是什麼」的契機。而我確實感受到,從那些我所遇到的精彩作品及其創作者那裡,接過了一個熱情的“接力棒”。我必須將這個接力棒延續到我自己的遊戲創作中……懷著這樣的新決心,我想在此次報告中畫下句點。
独特なコンセプトで武装したインディーゲーム 〜ゲームパビリオンjp 2025レポート〜【中編】
こんにちは、モブです。前回の記事に続き、ゲームパビリオンjp 2025レポートの第二回をお届けします。前回は「独特な雰囲気を醸し出すミニマルなインディーゲーム」として、小規模ながらも深い没入感を提供する作品を紹介しましたが、今回は少し趣向を変えて「独特なコンセプトで武装した、一方で闇を感じるインディーゲーム」に焦点を当てます。 インディーゲームの魅力の一つは、誰も思いつかなかったような斬新な発想や、それゆえの自由さにあります。今回紹介する二つのゲームは、まさにその魅力を最大限に生かし、一見すると明るく可愛らしい外観の下に、意外な「闇」や複雑さを秘めた作品です。 大阪のイベント会場で出会ったこれらのゲームは、プレイした瞬間に「こんな発想あったのか!」と驚かされると同時に、その裏に隠された深い思考に感心させられました。それでは、早速見ていきましょう。 超絶融合バビおじ症候群:ギャップがもたらすインパクト 続いて紹介するのは『超絶融合バビおじ症候群』です。カジュアルなリズムゲームというジャンルながら、バーチャル配信者をモチーフにした独特なコンセプトが目を引きました。なんと、中身はおじさんなのに見た目は美少女バーチャル配信者という主人公「しらぽん」が、人気配信者を目指す旅を描いているのです。可愛らしいUIとキャラクターデザインから感じられる闇のギャップが印象的で、思わずプレイしてしまったタイトルでした。 プレイ方法はシンプルです。三つのラインに沿って飛んでくるコメントのノーツを、スワイプ、タップ、ホールドを使って処理していくのです。一文で説明できるほど単純な仕組みなので、それほど難しくないだろうと安易に考えていた私の甘い考えを見事に打ち砕くように、このゲームの難易度は予想以上に高かいものでした。 イージー、ノーマル、ハードに分かれた難易度の中で無難にノーマルを選んだものの、なかなかついていくのが難しい。おそらく、会場という環境で曲をしっかり聴けず、動体視力だけでノーツを追いかけなければならなかったことが原因かと。また、慣れないスワイプ・タップ・ホールドという操作方法が相まって、そのような困難に直面したと思いつつですが…結果的に成績はCランク。わずか28人のチャンネル登録者しか獲得できないまま終了してしまいました。残念な結果でしたが、次のプレイヤーが待っていたため、そこで席を離れざる得ませんでしたね。 印象的な点と言えば、やはりゲームのコンセプトでしょう。バーチャルで美少女アバターで配信するおじさんとは…。アイデアとして思いつくことはあろうけれども、なかなか行動に移すのは容易ではない企画だと思います。その意味では、弊社レーベルの『ももっとクラッシュ』の「太ももで魂を挟んで浄化する」というコンセプトを連想させる部分もありました。 参考になったのは、やはりゲームの背景部分です。タイトル画面から暗く映し出される主人公の部屋の中が、あまりにもリアルで目が離せませんでした。黄ばんだ壁紙と薄暗い雰囲気の中のテレビやカレンダー、机の上に置かれたのは新聞とタバコ、そしてビール。そのような風景と対照的な「しらぽん」ちゃんがとにかく可愛いですと。コンセプトを単なるコンセプトで終わらせず、きちんとその闇を感じられるよう考え抜かれていることが伝わってきました。些細だけれども決して小さくない部分ですよね。 時間の関係で多くの会話はできませんでしたが、今回のイベントで初めて出会ったゲームだけに、今後の展開が楽しみです。次は東京のイベントで再会できることを期待しながら、次のゲームに移りましょう。 来りてモグモグ:記憶を手放す先に見える世界 次に紹介するのは『来りてモグモグ』です。イベントの出展情報で語られている説明によると超短編ノベルゲームとのこと。実際にノベルゲームコレクションで公開されたこの作品は、15分という短いプレイ時間を持っていましたが、その内容は決して短いものではありませんでした。このゲームの特徴を一言で表すなら「メタ性」ともいえるでしょう。 ストーリーは、ある日突然プレイヤーの前に現れた正体不明の存在が、ゲーム内に存在する五つの記憶のうち四つを渡さなければならないという話から始まります。主人公が渡せる五つの記憶とは、「名前」「言語」「現実」「音響」「色彩」とのこと。ここで選んだ選択肢は文字通りゲーム内から消えてしまい、プレイヤーはゲーム内のヒントを通じて最後の4つ目の記憶を渡すまでのエンディングを探っていくことになります。 記憶を渡すという独特の世界観と設定、そしてそれがゲーム内要素として反映されるという斬新な構造に興味を覚え、イベント開始前から注目していたゲームの一つでした。プレイ方式は文字通り選択型ノベルゲーム。難しく考える必要はなく、与えられた選択肢を選ぶだけのシンプルな方式ですが、この独特なシステムがプレイヤーに思考と好奇心の余地を与えていたのです。 例えば、私は最初に「言語」を選びました。なぜなら最初、「言語を特におすすめする」というセリフがあったからです。そうして言語を選ぶと、画面上のテキストが漢字と特殊記号が混ざった文字の集合体(言語モジュールが故障したときによく見るやつ)に変わってしまい、目の前の人物が何を言おうとしているのかも分からないまま手探りでゲームを進めることになります。しかも残りの4つの選択肢でさえも文字が崩れていたので、次に選んだものが何なのかさえ分からないまま選んでしまうという状況に陥ったほどです。 プレイ中に制作者さんから教えていただいたのは、記憶を失ったからといって必ずしも対処できないわけではないということ。例えば(少しネタバレになるので苦手な方は読み飛ばしてください)、言語の場合、ノベルゲームでよく見られるログ記録を通じて、相手が何を言ったのかを確認できるのです。このように、一見単純な選択肢を選ぶだけのゲームで、プレイヤーは自分の行動をより熟考し、その思考を通じて選択肢の結果をゲームのシステムで克服できるという独特な構造になっていました。 最も印象的だったのは、開発者との会話で聞いたこのゲームがティラノビルダーで作られたという点です。もちろん、ティラノスクリプトを直接編集する必要はあるとのことです。先ほど述べたノベルゲームコレクションで公開されたという言葉で既に察している方もいるかもしれませんが、個人的にティラノビルダーをあまり経験したことがない立場だったので、こんなゲームを作れるというのは正直ショックでした。 私も一時期ノベルゲームを制作する中でUnityの宴を使って色んなのチャレンジをしてきたのですが、当時見送ったティラノビルダーでもこんな素晴らしいゲームを作れるとは。「今更」という思いもありますが、今後ティラノビルダーで作られたノベルゲームコレクションのタイトルもしっかりチェックしなければ、そう思わせてくれた一本でした。 「表と裏」が織りなす魅力 今回紹介した『超絶融合バビおじ症候群』と『来りてモグモグ』、この二つのゲームを通じて感じたのは、インディーゲームが実現できる「表と裏」の魅力です。 表面的には可愛らしいキャラクターや親しみやすいUIを纏いながら、その実態は予想もしない内容や深みを持つ―これはある意味、より自由な発想と思考の行動ができる、インディーゲームなれではの試みとも言えるでしょう。 『超絶融合バビおじ症候群』では、美少女バーチャル配信者の裏にいるおじさんという設定自体がその二面性を表していますし、『来りてモグモグ』においては、選択によって失われる「記憶」という要素が、プレイヤー自身の体験そのものを変質させていきます。 大阪で出会ったこれらの作品は、「ゲームとは何か」「体験とは何か」という根本的な問いかけをも含んでおり、プレイ後もしばらく頭から離れない余韻を残してくれました。 次回の第三回では「デザインと操作感に心血を注いだインディーゲーム」と題して、インディーながらもメジャータイトル顔負けの完成度を誇る三つの作品をご紹介します。お楽しみに。