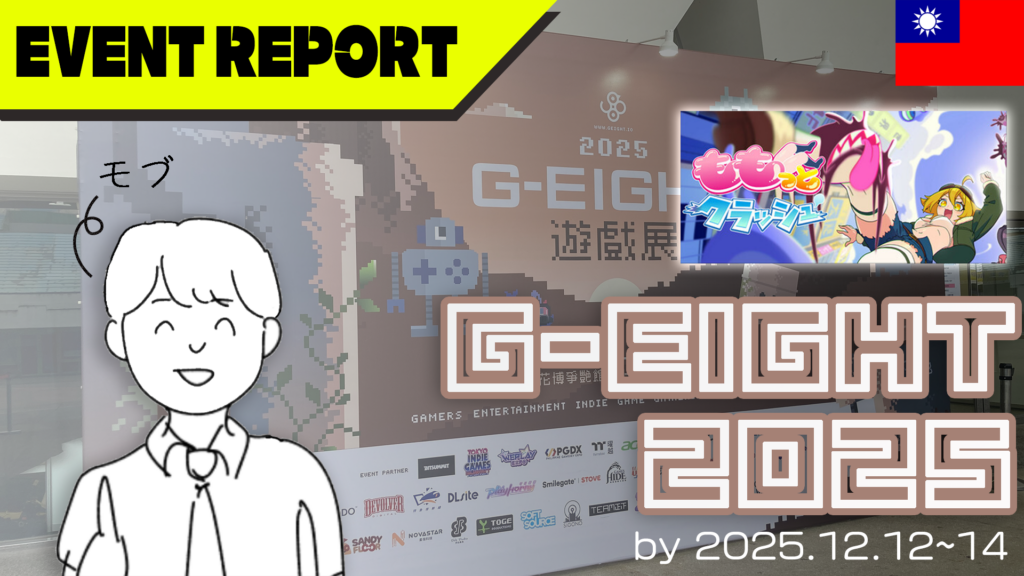こんにちは、SKOOTAGAMESのネゴラブチームに所属しております、モブです。 日本はすっかり冬の寒さに包まれている頃かと思いますが、私は少し前まで、海を渡った南の島、台湾にいました。12月だというのにコートがいらないほどの暖かさ。しかし、それ以上に私を驚かせたのは、現地のユーザーたちが放つ、季節外れの真夏のような“熱気”でした。 今回は、12月12日から14日にかけて台北で開催されたインディーゲームの祭典「G-EIGHT」に、我々SKOOTA GAMESが出展者として参加した際の記録をお届けします。 我々が持ち込んだのは、日本国内のイベントでも(主にその設定で)話題を呼んだ『ももっとクラッシュ』。「太ももで敵を挟んで浄化する」という、文字にすると少々…いや、かなり衝撃的なコンセプトを持つリズムアクションゲームです。 果たして、この日本独特の(?)ユニークさが、海を越えた台湾の地でどのように受け入れられたのか。日本とは少し違う、台湾ユーザーの驚くべき反応と熱量について、レポートしていきたいと思います。 「恥ずかしさ」を「好奇心」が超える瞬間 まず、正直にいいましょう。日本で展示を行う際、この「太ももで挟む」というビジュアルや設定に対して、多くのユーザーは少し恥ずかしがったり、遠巻きに見守ったりする反応が一般的でした。それはある意味、地域や年齢による慎ましさとも言えるかもですが。 しかしながらこのようなユーザーの反応に顔をそむけることはしません。むしろ今回、私たちはあえて“太もも”を隠すことなく、ブースに42インチの巨大モニターを設置し、プレイ映像を堂々と流すことにしました。完全アウェイの地で、我々の誇るべき“太もも”の姿を一人でもより多く届けたかったからです。 結果は、予想以上のものでした。通りがかった台湾のユーザーたちは、巨大モニターに映るシュールな光景を見て、最初はやはり笑ったり驚いたりしてくれていました。ですが、普段と決定的に違ったのは、その「このゲーム面白そう」の笑いが即座に「気になるからプレイしてもよう」の行動にと繋がったわけです。 「太ももでこんなことをするなんて!」という指摘要素より「なんだこれは?」という好奇心が先を走り、恥ずかしがる暇もなくコントローラーを握る。そしてひとたびプレイすれば、そのアクションの手触りに没頭してくれる。さらにプレイしたユーザーのほとんどは、その場で自然にSteamアプリを開き、ウィッシュリストに登録してくれていました。「面白かった=即登録」という、この直感的な行動力には、開発者として本当に救われる思いでした。 言葉の壁は“太もも”で越えられる 我々にとって最大の懸念だった「言語の壁」も、意外な形で乗り越えることができました。 中国語が全く話せない私たちが、このゲームの「太ももで挟む」というニュアンスをどう伝えたか。それはもう、身振り手振り…いえ、「太もも振り」でした(笑)。 言葉で説明するよりも早く、私たちスタッフが自らの太ももを動かして「こうやって挟むんだよ!」「キュートでファニーなリズムゲームなんだ!」と体で表現する。すると、ユーザーもすぐにその意図を理解し、笑って頷いてくれるのです。ゲーム自体はキーボードやコントローラーで遊ぶ一般的なPCゲームですが、そのコンセプトを伝えるためのパフォーマンスが、言葉以上のコミュニケーションツールとなりました。 「これ面白いからやってみなよ!」:シェアする文化の健全さ また、会場で特に印象的だったのが、台湾ユーザーの「シェア文化」です。 一人で試遊を楽しんだユーザーが、しばらくすると友人を連れて戻ってくる。「これ、すごく面白かったからお前もやってみなよ!」と、まるで自分のことのように友人に勧める。すると友人がプレイして笑っている姿を見て、自分もまた楽しそうに笑う。 普段のイベントでは「一人でじっくり楽しむ」ことが多いのに対し、台湾では「面白い体験を周りと共有し、一緒に楽しむ」という意識が非常に強いように感じました。 それを裏付けるように、プレイ後の感想を付箋に書いてもらうようお願いしたところ、なんと10人中7人という高い割合で、快くメッセージを残してくれました。好きなものを好きだと表現する、面白いものを周りに広める。この台湾ユーザーのとある意味ストレートで「健全」な熱量が、会場全体のポジティブな空気を作っているのだと実感しました。 祭りのあと、そして“私の魂”も挟まれる…!? 初めての台湾出展は、単なる海外進出以上の意味を持つものでした。「太もも」という際どいテーマであっても、そこに確かな面白さと熱意があれば、国境も言葉も関係なく受け入れられる。台湾のユーザーたちが教えてくれた、「好き」を隠さず表現する情熱。その熱を『ももっとクラッシュ』に込め、これからは日本、そして世界中のプレイヤーへと届けていきたいと思います。 さて、そんな熱気に後押しされ、我々SKOOTAGAMESも重大な決断をいたしました。 現在Steamで開催中のウィンターセールに合わせ、『ももっとクラッシュ』も大型アップデートを敢行! さらに、季節感を全力で無視した台湾とは裏腹に、こちらはしっかりと冬を楽しむ「クリスマス衣装DLC」も発売いたしました。 ですが、今回のアップデートの目玉は衣装だけではありません。なんと、「太ももに挟まれて浄化される魂のボイス」が新たに追加されたのです! 追加されたボイスは全8種類。…そして、ここで皆様に懺悔しなければならないことがあります。実はその8つの魂の中に、あろうことか私、モブの声が一つ混ざっております。 ご覧ください、この収録スタジオでの悲壮感あふれる写真を。 「いや、そこでもっと喜びを覚える感じで!」という繊細なディレクションを受けながら、私の魂(と声帯)は完全に太ももに捧げられました。まさかゲーム開発を始めて、自分の絶叫が世界中のプレイヤーの太ももに挟まれる未来が来るとは、夢にも思いませんでした…。 どの声が私のものなのか、それはプレイしてのお楽しみということで(笑)。ぜひSteamで『ももっとクラッシュ』をチェックして、台湾の熱気と、私の魂の叫びを感じてみてください。 それでは、また次回のレポートでお会いしましょう! メリー・フトモモ・クリスマス!
休日出勤のゲムダン8で見つけたのは―日常の“裂け目”を覗く三つのゲーム【前編】
こんにちは、SKOOTAGAMESのネゴラブチームに所属しております、モブです。キーボードを叩いたり、たまに代表のコーヒーを淹れたりしながら、日々ゲーム開発という大海を漂っております。 さて、先日5月4日、ゴールデンウィークの真っ只中に開催されたインディーゲームの祭典「東京ゲームダンジョン8」に、何を隠そうこの私、そして我らがSKOOTAGAMESが、なんと初めて「出展者」として参加してまいりました。これまで二度ほど、いち来場者としてレポートを書かせていただいたこのイベントに、まさか自分たちのブースを構える側になるとは…。正直なところ、カレンダーの赤い日に会場へ向かう自分の背中を見ながら、「なぜ私は連休に働いているのだろう…」という哲学的な問いが、ほんの少し、ほんの少しだけ頭をよぎらなかったと言えば嘘になります(苦笑)。 しかし、ご安心ください。結論から申し上げますと、そんな些細な心の声などあっという間に吹き飛んでしまうほど、今回の東京ゲームダンジョン8は、熱気に満ち溢れた素晴らしい一日でした。3100人もの方が来場されたという会場は、連休中ということもあってか、ユーザーの方々はもちろん、開発者同士の交流もかつてなく活発だったように感じます。まあ、私たちが初出展だったから、そう見えただけかもしれませんが…。それでも、普段とは違う「作り手」としての視点でイベントの空気に触れ、たくさんの刺激的なゲームやクリエイターの方々と出会えたのは、本当に貴重な体験でした。 というわけで、今回のレポート【前編】では、そんな初出展のドタバタ 속(?)で、私モブのアンテナに特に強く引っかかった、独特の雰囲気を纏う三つの作品をご紹介したいと思います。ジメジメとした梅雨、そしてその先に待つ蒸し暑い夏を前に、ちょっと背筋が涼しくなるような、あるいは心がザワつくような、そんな個性的なゲームたちです。 Machico:モノクロ洋館で出会った、奇妙な“強烈さ” さて、今回の東京ゲームダンジョン8で、私が最初に足を踏み入れたのは、どこか懐かしい雰囲気と強烈な個性が共存するブースでした。スタジオジョニーさんが制作中という、『Machico』。ジャンルとしては2Dのホラー探索アドベンチャーゲームとのことですが、試遊台で体験できたのは、そのほんの入り口、ほんの10分にも満たない短い時間でした。 物語は、急に姿を消した友人を探し、古びた洋館へと足を踏み入れた主人公が、そこで不可解な出来事に巻き込まれていく…という、ホラーゲームの王道とも言える導入部から始まります。薄暗い洋館の中を一人、手探りで進んでいく感覚は、かつて夢中になった『青鬼』のような、あの頃のヒリヒリとした緊張感を思い出させてくれましたね。 しかし、この『Machico』が単なる懐古趣味に留まらないのは、その独特なアートスタイルと雰囲気作りにあると感じました。画面全体を覆うのは、 まるで古いモノクロ映画か、あるいは往年の恐怖マンガの一場面を切り取ったかのような、ざらついた質感の白と黒の世界。キャラクターも背景も、そのほとんどが陰影と黒い線で描かれており、見慣れない洋館の不気味さを一層際立たせています。このビジュアルが、探索という行為そのものに言いようのない不安感を付与し、「何かが出てくるんじゃないか」という原始的なホラー感をじわじわと煽ってくるんです。 そして、その予感は的中し、探索を進めるうち、突如として現れる異形の追跡者…。動物のような頭部を持ち、車椅子に乗りながら、その車輪にはなんとチェーンソーが取り付けられているという、一度見たら忘れられない強烈なデザインの“何か”が、こちらを執拗に追いかけてくるのです。その姿を目撃した瞬間、かつてインディーゲームシーンで話題を呼んだ『Year of the Ladybug』の、あのコンセプトアート群が脳裏をよぎりました。生理的な違和感と、どこか目を離せないような倒錯的な魅力が混じり合った、あの衝撃に近いものを感じたのです。 実はこの『Machico』、今回ご紹介する中でも特に、私自身が今後の展開に大きな期待を寄せている一本でもあります。というのも、制作されているスタジオジョニーさん、実は普段アニメーションを手掛けていらっしゃるチームだそうです。公式サイトで拝見した彼らの他のアートワークは、本作とはまた趣の異なる、温かみのある繊細なタッチで描かれたものが多かったのですが、その中にもどこか共通する“寂しさ”や“切なさ”のようなものが感じられ、それがこの『Machico』のミステリアスな雰囲気と不思議と響き合っているように思えたのです。 『Year of the Ladybug』が、いくつかのコンセプトアートだけで多くのゲーマーの想像力を掻き立てたように、現在進行形で制作が進んでいるこの『Machico』が、一体どんな完成形となって私たちの前に姿を現すのか…それを考えると、今から楽しみで仕方ありません。短い試遊時間ではありましたが、そんな未来への期待を抱かせるには十分すぎるほどの、“何か”を感じさせてくれる作品でした。 The Doppel:二色の悪夢で響く、己と向き合う“逃走劇” 『Machico』のブースを後にして、次に向かったのは、どこかミニマルながらも強烈な個性を放つ一角でした。こちらの作品は『The Doppel』。白と黒、わずか二色だけで構成された悪夢の世界を舞台に、自分自身を模した存在「ドッペル」からひたすら逃げ続けるという、シンプルなルールの2Dアクションゲームです。 主人公は、締め切りとプレッシャーに追われる小説家。そんな彼が、けたたましく鳴り響く出版社からの電話を取った瞬間、悪夢の世界へと引きずり込まれるところから物語は始まります。この導入だけでも、なんだかこう…記事を書いている人間にとっては、他人事とは思えないような妙な感覚を覚えましたね(苦笑)。 悪夢の中の主人公は、その名の通り自らの動きを忠実に模倣して追いかけてくる「ドッペル」から逃れるため、前へ前へと進まなければなりません。面白いのは、このゲームにおける光と闇の扱いです。暗闇の中にいる間は「ドッペル」もプレイヤーの前に出てこず、プレイヤーは完全にセーフ状態。しかし、一歩でも明るい場所へ踏み出せば、どこからともなく「ドッペル」が現れ、執拗な追跡が始まるです。そして、「ドッペル」との距離が縮まるにつれて、まるで主人公の気力そのものが吸い取られていくかのように、じわじわと体力が削られていくのです。 マップには様々なギミックも配置されており、ただ闇雲に突っ走るだけではすぐに「ドッペル」の餌食。試遊では、まず暗闇で安全を確保しつつマップの構造やギミックの動きを観察し、タイミングを見計らって一気に駆け抜ける…という、さながら往年の『バーガータイム』や『ロードランナー』のような、古き良きアーケードゲームを彷彿とさせる歯ごたえのあるアクションを体験できました。このシンプルながらも奥深いゲーム性には、思わず唸らされましたね。 しかし、この『The Doppel』が私の心に深く刻まれたのは、単にゲームとしての面白さだけではありませんでした。むしろ、プレイを終えて会場を後にした後に、じわじわとそのテーマ性が反芻された、とでも言うべきでしょうか。考えてみれば、このゲーム、別に無理して光の中へ進む必要はないんです。暗闇にさえいれば、少なくとも「ドッペル」に襲われる心配はなく、安全は保障されている。それでも、物語を進めるためには、光の中へ飛び出し、自分自身の影とも言える「ドッペル」と対峙しなくてはならない…。 この構造が、締め切りというプレッシャー、そしてそこから逃れたいという小説家の心理状況と、あまりにも見事にリンクしているように感じられたのです。すべてが二色だけで表現された世界もまた、安全な暗闇に留まるか、それとも困難に満ちた光の中へ進むかという、二者択一の厳しい現実を象徴しているかのようでした。逃げているようでいて、実は自分自身の内面と向き合わされているような、そんな不思議な感覚。短い試遊時間でしたが、このゲームが投げかける問いは、私の心に深い余韻を残してくれました。 新宿異変:夜の街角、一枚の写真に刻まれる複数の“結末” さて、今回のレポート【前編】でご紹介する最後の作品は、その強烈なキービジュアルに吸い寄せられるように足を運んだ『新宿異変』です。こちらは、夜の新宿を舞台に、街に潜む様々な怪異現象を写真に収めていくという、ホラーテイストの短編ビジュアルノベルといった趣の作品でした。試遊時間はわずか5分から10分ほど。しかし、その短い時間の中に、このゲームならではの個性がギュッと凝縮されていましたね。 ゲームが始まると、プレイヤーは簡単な状況説明と共に、どこか静かな夜の新宿の街へと放り出されます。そこで遭遇する、人ならざる“何か”の気配…。プレイヤーの目的は、これらの怪異現象をカメラで撮影すること。ただし、ここがこのゲームのキモでして、「適切な距離を保って」シャッターを切らなければなりません。対象に近づきすぎれば、正体不明の恐怖に呑み込まれてゲームオーバー。かといって、遠すぎれば何も写せず、成果もなし。まさに一瞬の判断と度胸が試される、緊張感あふれるシステムです。 私がこのゲームに強く惹かれたのは、何を隠そう、ブースで目にした一枚のキービジュアルでした。人型ではあるものの、明らかに“こちら側”の存在ではない、形容しがたい違和感を纏ったその姿…。どこかで見たような…そう、昨年デモが公開され、大きな注目を集めた『No, I’m not a Human』の、あの不気味ながらもどこか目を離せない魅力を持ったビジュアルに通じるものを感じたのです。こういう、一目見ただけで「何かヤバそうだ」と思わせるセンス、個人的にとても好みです。 そして、この『新宿異変』を語る上で外せないのが、「マルチエンディング」という要素でしょう。驚いたことに、この短い試遊版ですら、その片鱗を十分に味わうことができたのです。実は私、自分のプレイ前に、偶然お二方ほど他の方のプレイを後ろから拝見する機会があったのですが、なんと私を含めた三人の結末が、それぞれ全く異なっていたんですよ。もちろん、先ほども触れたように、このゲームは一歩間違えれば即ゲームオーバーという、いわゆる「死にゲー」的な側面も持っているので、それも多様な結末に繋がりやすい一因だとは思います。ですが、それにしたって、この短時間でこれだけ体験の幅を持たせているのは、単純にすごいな、と。 イベント会場で気になるゲームの試遊待ちをしていると、前の人のプレイで内容が分かってしまって、自分の番が来た時には少し興味が薄れてしまった…なんて経験、ありませんか? 特にストーリー重視のノベルゲームでは、それが致命的になることも少なくないと思うんです。その点、この『新宿異変』は、短い試遊の中に多様なエンディングを用意することで、何度見ても新しい発見があり、むしろ「他のエンディングも見てみたい」と思わせる。これは非常にクレバーな作りだと感じましたし、実を言うと、我々ネゴラブチームのゲーム制作においても、大いに参考にすべき点ではないかと、一人静かにメモを取った次第です。 日常の裂け目から垣間見た、三者三様の“気配”と次なる予感 というわけで、ゴールデンウィークの中、初めての出展という慣れない体験の合間を縫って巡り合った、私モブの心を特に強く捉えた三つのゲーム、『Machico』、『The Doppel』、そして『新宿異変』をご紹介してまいりました。 モノクロームの悪夢の中でアニメーションスタジオの新たな挑戦と未来への期待を感じさせてくれた『Machico』。二色だけで描かれた世界で、自分自身の影と向き合う逃走劇を強いた『The Doppel』。そして、夜の新宿という日常のすぐ隣で、無数の怪異と幾通りもの結末を突きつけてきた『新宿異変』。 どれも、日常に潜む「裂け目」から、得体の知れない「何か」が顔を覗かせているような、そんなヒリヒリとした感覚を呼び覚ます、個性的な作品たちでしたね。もちろん、初出展の身としては自分のブースのことで手一杯だったため、全てのゲームをじっくり堪能できたわけではありませんが、それでも作り手として参加したからこそ得られた刺激は、確かにあったように思います。 まあ、お世辞にも「最高な休日」とは言えませんでしたが、それでもこうして心に残る作品たちと出会えたのですから、結果オーライ、ということにしておきましょう。きっとそうです。 さて、この東京ゲームダンジョン8のレポートは、まだまだ終わりません。【後編】では、また少し毛色の異なる、しかしながら同様に強烈な個性を放つゲームたちをご紹介する予定です。果たして、次にお届けするのはどんな“裂け目”からの誘いなのか…。 ラブコメ X