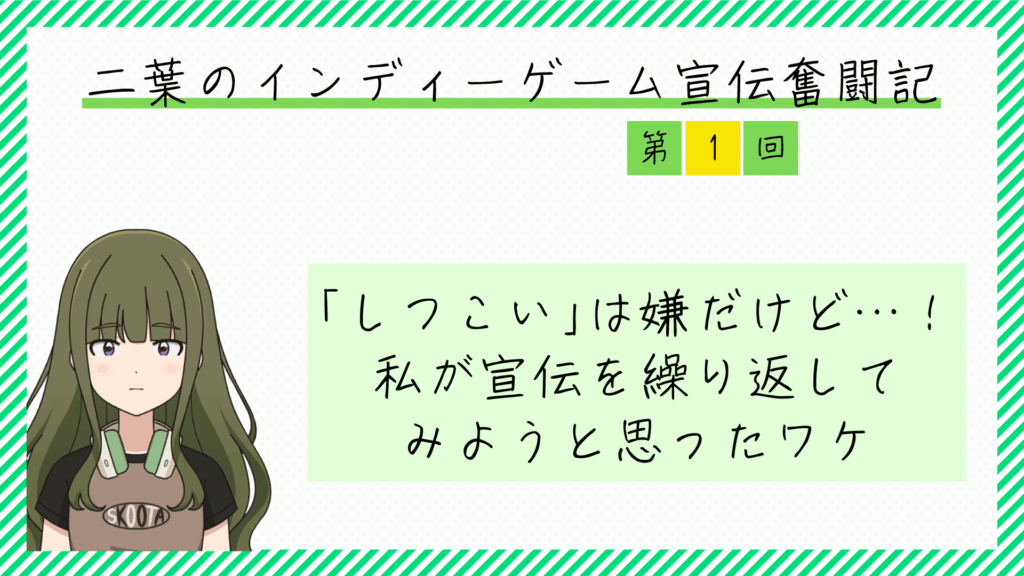ニーハオ! SKOOTA編集部のイ・ハナと申します。 皆様、モブくんが届けてくれた「私の魂が太ももに挟まれた話(G-EIGHTレポート)」や「お気に入りゲーム紹介(TpGSレポート)」は、もうお読みになりましたでしょうか? 彼が台湾の熱気に包まれながら楽しんでいたその隣で、実はわたくし、少しだけ冷や汗をかいておりました。 なぜなら私、中国語はおろか英語も自信がないという、まさに「語学力:サバイバルレベル」の状態で台湾に上陸してしまったからです。 「まあ、何とかなるでしょう!」という謎の自信は、空港に降り立った瞬間に揺らぎ始めました。しかし、ここで奇跡が起きます。なんと、台湾のゲーマーの方々の多くが、私の拙い日本語を理解してくださるではありませんか! アニメやゲームの影響でしょうか、簡単な日本語であればスムーズに意思疎通ができる環境に、私は心底救われました。 とはいえ、やはり自分が直接、海外のクリエイターに深い話を伺うのはハードルが高いのも事実。そんな中、今回のTaipei Game Show(以下、TpGS)のインディーゲームエリア「Indie House」には、驚くほど多くの韓国インディーゲームが出展されていました。 普段、日本のイベントではなかなか接する機会のない母国のゲームたち。言葉の壁に少し疲れていた私にとって、そこは開発者の方と直接深い話ができる、数少ない貴重な場所でもありました。 というわけで今回は、あえて注目の期待作『NAMMO』などは(モブくんのレポートに譲るとして)少し置いておきましょう。私が会場で出会ったのは「まだ見ぬ韓国インディーゲームの可能性」といっても過言ではない、4つの作品です。それでは、ご紹介させていただきます。 🦀 スーパーキングクラブシミュレータ:235円で買える、破壊とカニのユートピア まず最初にご紹介いたしますのは、Skago Gamesさんが制作した『スーパーキングクラブシミュレータ(Super King Crab Simulator)』です。 タイトルからして既に「何か」が起きていますが、内容はさらに強烈です。プレイヤーは巨大なズワイガニとなり、人間に捕らわれた同胞を救い出すために、平和な海岸都市を慈悲なく破壊し尽くすという、なんともぶっ飛んだコンセプトのアクションゲームとなっております。 一見すると、いわゆる「バカゲー(褒め言葉)」の類に見えますし、実際にそうなのですが、コントローラーを握ってみると、その手触りの良さに驚かされました。 カニになって街を破壊するなんて、言葉にするとなかなか想像しにくい体験ですが、あえて例えるなら昔遊んでいた『Prototype』シリーズや『GTA』シリーズといった、かつてのオープンワールドゲームを思い出させるプレイ感に近い印象でしょうか。 人や建物がひしめく箱庭のような空間を、カニ独自の動き(とはいえ非常に高速です!)で縦横無尽に駆け巡り、目に入るオブジェクトを片っ端からハサミで粉砕していく。「新しい」というよりは、どこか「実家のような安心感」すら覚える、プリミティブな破壊の楽しさがそこにはありました。 そして、私がこのゲームを是非レポートに残したいと思ったもう一つの理由は、ローポリゴンのシンプルなグラフィックの中に隠された、驚くべき「ディテール」へのこだわりです。 これはもしかすると、私のような韓国出身のプレイヤーにしか伝わらないポイントかもしれませんが…マップ上の建物のデザインや看板のテキストが、思わず笑ってしまうほど「リアルな韓国」なのです。 あえてローカライズされずハングルそのままで残されておりましたが、飲食店のメニューや巨大な商号、そして何より、お店や住宅の裏手に雑多に置かれた室外機や、それを囲むブロック塀の質感。日本や台湾の風景とは微妙に異なる、しかし韓国人なら誰もが「あるある!」と思える生活感あふれる風景が、絶妙な解像度で再現されています。この「知っている街」をカニになって破壊する背徳感は、なかなかに得難い体験でした。 開発者の方の遊び心も随所に光ります。「美味しく破壊しろ」というキャッチコピーや、レベル(Level)の表記をキングクラブにかけて「Kevel」とするなど、思わずクスリとしてしまう小ネタが満載です。こういった細かい発見が積み重なることで、単なるアクションゲーム以上の愛着が湧いてくるのですね。 そして何より強調したいのが、そのコストパフォーマンスです。Steamでの価格はなんと235円(日本基準)。 同胞を救うために街を壊すという明快すぎるストーリー、誰もがすぐに楽しめる直感的な操作、そして作り込まれた小ネタの数々。これらがこの価格で提供されていることは、ある意味で奇跡的です。「安かろう悪かろう」ではありません。「暇だし、カニになって街でも壊してみるか?」という軽い気持ちに、全力で応えてくれる最高のエンターテインメントなのです。 もし今、あなたが少し退屈しているなら、迷わずこのカニの甲羅を被ってみることをお勧めいたします。 🎒 下校道:ノスタルジーという名の恐怖、2010年代の教室にて 次にご紹介いたしますのは、先ほどの陽気なカニの世界とは打って変わって、静寂と闇が支配するサバイバルホラーゲーム、『下校道(Hagyo-gil: The Way Home)』です。制作は、「スタジオ不完全燃焼」さん。 会場でプレイできたデモ版は10分ほどの短い内容でしたが、その密度たるや、短編映画一本を見終えたかのような重厚な体験でした。 物語は至ってシンプル。ある日、学校の教室で一人目覚めた主人公が、外へ出るために手がかりを集めて脱出を試みるというものです。何の説明もなく放り出される導入には戸惑いますが、探索を進めるにつれ、古びた設備や封鎖された出入り口といった不穏な違和感に気づき、「この学校はどこかおかしい」と肌で理解することになります。 そして最後には、制服を着た女子学生の姿をした「何か」が現れ、プレイヤーは手に持ったモップで必死に抵抗することになるのですが…ええ、私は勝てませんでした。モップを握りしめたまま、無惨にもゲームオーバーとなりました(涙)。 「見知らぬ場所に閉じ込められる」という設定自体は、ホラーゲームにおいて決して珍しいものではありません。しかし、この作品が他の追随を許さない圧倒的な魅力を持っているとすれば、それは「狂気的なまでの空間の再現度」にあります。 先ほどの『スーパーキングクラブシミュレータ』が、シンプルなグラフィックの中に記号的な「韓国らしさ」を込めた作品だとするなら、この『下校道』は、空気や湿度、当時の時間までもそのままゲームの中に閉じ込めようとしたかのような、恐ろしいほどのリアリズムを追求しています。 舞台となるのは、おそらく2010年代の韓国の中学校、あるいは高校でしょうか。 まさに私が学生時代を過ごした時期と重なるその風景は、ただ「リアル」なだけではありません。教室の空気の匂い、廊下に響く足音、机の質感…視覚情報だけのはずなのに、かつての記憶が呼び覚まされ、五感が刺激されるような錯覚に陥りました。国籍を問わず、インディーゲームという枠組みの中でこれほどのグラフィック表現にお目にかかることは、そうそうないでしょう。 ただ懐かしいだけなら良い思い出ですが、その「あまりにも慣れ親しんだ空間」に、少しずつ異質なノイズが混ざり込んでいく過程こそが、このゲームの真の恐怖です。 よく出来たホラー映画の導入部を自らの足で歩いているかのような没入感。残念ながら現時点ではSteamなどのオンラインストアには公開されていないようですが、いつか製品版として世に出た暁には、ぜひ日本の皆様にもこの「美しくも恐ろしい下校道」を体験していただきたいと強く願っております。 🍽️ GLUTTONY:食欲こそが力! 悪魔的「満腹」ハック&スラッシュ 三番目にご紹介するのは、Team
「しつこい」は嫌だけど…! 私が宣伝を繰り返してみようと思ったワケ – 二葉のインディーゲーム宣伝奮闘記 #1
こんにちは。SKOOTA編集部の月森二葉です! 実は私、SKOOTA編集部で記事作りにくわえて、4月からSKOOTA GAMESでインディーゲームの宣伝・リリースを担当することになりました! まだ担当になったばかりで、今は右も左も分からない状態なんですが、どうすれば自分たちのゲームを多くの人に知ってもらえるか、インディーゲームについて、日々勉強中です! この記事を読んでいる皆さんは、きっとご自身でもゲームを作られていたり、インディーゲームに詳しかったりする方も多いと思います。私もいちゲーマーとして普段から色々なゲームに触れているんですが、その中でずっと思っていたことがあるんです。 良さげなゲームと出会うの、難しすぎる! そう思いませんか? 情報が溢れる今の時代、「これだ!」と自分の好みにピッタリ合うゲームを見つけるのって、結構大変ですよね……。もちろん、探すこと自体が楽しい、というときもあるんですが。 これは私たちのようなゲームをリリースする側にとっても同じく、いや、もっと大きな課題です。たくさんのゲームや情報の中で、どうすれば自分たちのゲームが埋もれてしまわずに、プレイヤーの皆さんの目に留まるんだろう? これはまさに私たちが日々頭を悩ませている切実な問題ですが、同じように悩んでいる開発者の方も多いんじゃないでしょうか? この疑問をどうにかしよう! と色々調べたとき、まずは「多くの人に見てもらうこと」が大事で、そのためにもゲームの顔となる「ストアページの見せ方」や「紹介トレイラーの作り込み」みたいな、基本的な工夫が大事! と書いてあることが多いんじゃないでしょうか。もちろんこれは、もうホントその通り! ……なんですけど、そういう情報って、既に色々なところにありますし、皆さんもよく意識されてますよね。 一方で、いざ具体的にやってみよう! って思うと、「基本は分かった! でも、じゃあ次に何を、どんな順番で、何に気をつけてやればいいの!?」みたいに、具体的だったり細かいところで迷ったり、情報が足りないなーって感じたりしませんか?(少なくとも初心者の私は、まさにそこで「うーん!」ってなっちゃってます!) そこでこの連載では、「ストアページの見た目を良くしよう!」、「すごいトレイラーを作ろう!」みたいな一つの要素を作り込むお話はちょっと横に置いといて、そういう「いざやるぞ! って時に迷っちゃうポイント」とか、「言われてみれば確かに!」って見落としがちな視点に注目して、私なりに調べて「なるほど!」って思ったことや、多くの人が楽しんでいる作品を生み出した人たちがどう工夫してるのか、みたいな情報を皆さんと共有していきたいと思います! 記念すべき第1回のテーマは、そんな情報発信の根幹に関わるかもしれない「宣伝の『繰り返し』」について。「何度も同じこと言ったらウザいかな……?」みたいに、私が最初に「うーん!」と悩んだこのポイントについて、調べて考えたこと、そしてそれをもとにやってみようと計画していることをお話しします! この記事が、皆さんのゲームを多くの人に届けるためのヒントになったり、「よし、こうしてみよう!」って思うきっかけになったら、すごく嬉しいです! 私も学びながらなので、ぜひ一緒に考えていきましょう! 一回言ったら、もう終わりでいい? さて、今回のテーマは「宣伝の繰り返し」です。 ゲーム開発をしていると、発信する情報って本当に色々ありますよね。渾身のトレイラー公開や発売日発表みたいな大きなニュースはもちろん、日々の開発進捗、ちょっとしたゲームのTips、イベント出展のお知らせとか、本当に様々。 【も知らせ】3/29 #ゲームパビリオンjp2025 🍑「ええっ!? ふとももで…魂を…挟む!?」 そう、これが「ももっとクラッシュ」。あなたの想像を超えた新感覚リズムゲームを、現在制作中です!今回、ブース『う-5』にて新キャラ実装のバージョンでお待ちしています🦵#SKOOTAGAMES #ももクラ pic.twitter.com/L7GpmS42af — 【公式】SKOOTA GAMES🎮25/05/04@東京ゲームダンジョン8【3T-6】初参戦💪 (@SKOOTAGAMES) March 28, 2025 ゲーム作りには情報発信はつきもの。どんな発信もできれば沢山の人に見て、楽しんでもらいたいですよね。 で、そういう情報を、例えばSNSで「よし、投稿したぞ!」って発信する時って、なんとなくそこで「はい、伝達完了!」みたいな気持ちになっちゃいませんか?(私はそうでした) でも、本当に一回だけで「伝わった」って、結構不安じゃないですか? 反応が少ないことも多くて、むしろ「ちゃんと届いたかな?」「見てもらえたかな?」って、どこか不安が残ったり。だからこそ、「もう一度言った方がいいかな?」って思うわけですが、いざ「同じような話を繰り返す」となると、ためらいが生まれてしまう……。そんな経験、ありませんか? 私はまさにそれで、「一度言えば伝わるはず」「何度も言うのは、なんだか申し訳ない気もするし、迷惑かも」って、どこかで無意識に「繰り返し=悪」みたいに思い込んでいたフシがあります。(皆さんはどうですか?) でも、自分が「受け手」になったら……? そんな風に悩んでいたある時、ふと「じゃあ、自分が好きなコンテンツの情報だったらどうだろう?」と考えてみたんです。自分が心待ちにしているゲーム、大好きなアニメや漫画、応援しているクリエイターさんの活動……。 思い返してみると、例えば「待望のゲームの発売日が決定!」とか「好きなアニメの続編制作が決定!」みたいな自分にとって“大事な”ニュースって、発表直後だけじゃなくて、発売日が近づいてきたり、新しい情報が小出しにされたりするたびに、何度見かけてもむしろ嬉しいのかなって思いました。 「おお、もうすぐ発売だ! 予約しなきゃ!」とか、「そういえば、特典情報ってどうなってたっけ?」とか、「この前見逃してたPV、やっぱり最高!」みたいに、繰り返し情報に触れることで、期待感が高まったり、情報を補完できたり、熱量を再確認できたりする。そんなポジティブな体験の方が多い気がしたんです。 「大事な情報」は、繰り返してこそ届くのかも この「受け手としての感覚」は、けっこう大きな発見でした。もちろん、どんな情報でも繰り返せば良いというわけではないと思います。興味のない人にとってはノイズになり得るし、伝え方や頻度には工夫が必要なのは間違いないはず。 でも、少なくとも、私たちのゲームを「気になる」「面白そう」と思ってくれている(かもしれない)人たちにとっては、重要な情報を適切な形で繰り返し届けることは、必ずしも「悪」ではなくて、むしろ、届けたい相手にとっては『親切』や『責任』って側面もあるのかも……? なんて、少しずつ思うようになったんです。 実際、あるアニメのアカウントでは、「最初のお知らせより、二度目のお知らせの方が倍近くも話題になった」なんていう話もあるくらいです。 これ、すごく面白いですよね! なんで、そのアカウントでは二回目のお知らせの方がグッと話題になったんでしょうか? もしかしたら、最初の投稿は見逃していた人や、その時はまだピンと来てなかった人も、二回目の投稿までの間に他のニュースとかで見て『あ、これ気になるかも!』って気持ちがだんだん温まってきていたタイミングだった、とか……? そういう、受け取る側の準備みたいな理由もあるのかなあ。いずれにしても、タイミングや文脈次第で、情報の響き方って本当に変わるんですね。 💐••┈┈┈┈ TVアニメ化決定「きみが死ぬまで恋をしたい」 ┈┈┈┈••💐 「生きたい」なんて、知らなかった。 🪄https://t.co/pLrtx4tPGS#きみ死ぬアニメ pic.twitter.com/zIDKDew9DM —
出会いは終わらない!雨の川越インディー探訪~ぶらり川越 GAME DIGGレポート【後編】
こんにちは、モブです。SKOOTAGAMESのネゴラブチームに所属しています。雨の中お届けした川越 GAME DIGGレポート、今回はその【後編】となります。 【前編】では、一杯のうどんに地域コミュニティの熱い想いが込められていた『湯斬忍者』、そして「コエトコ」という特別な空間で、プレイヤー自身が旋律を奏でるという忘れられない音響体験をさせてくれた『MeloMisterio -play your melody-』という、雨の中でも際立つ個性を持った二つの作品をご紹介しました。どちらも、単にゲームシステムが面白いという評価だけでは語り尽くせない、深い余韻を私の中に残してくれましたね。 さて、この【後編】で焦点を当てるのは、もう少し個人的な感覚や記憶、あるいは遊びの本質といった部分に、より深い印象を受けた二つの作品です。それは、画面を通して作り手の優しい眼差しそのものに触れるような感覚であったり、あるいは、すっかり忘れていた「みんなで集まって遊ぶ」ことの原風景を、鮮やかに思い出させてくれるような体験であったり。 一つは、まるで会場となった川越の、あの日の雨上がりの空気までも丁寧に描き出しているかのような、温かく優しい雰囲気のゲーム。そしてもう一つは、難しい理屈は抜きにして童心に返り、思わず声を上げてしまうほど、協力して遊ぶことのプリミティブな熱狂と楽しさを、改めて実感させてくれたゲームです。 どちらの作品も、あの日の雨の中で、そしてぶらり川越 GAME DIGGという少し変わったイベントだからこそ出会えたからこそ、より強く私の記憶に刻まれているのかもしれません。では、【後編】最初の作品となる、心温まる里山の冒険から、じっくりと見ていくことにしましょう。 里山のおと 春さんぽ:雨音に溶け込むタヌキの小さな冒険と、忘れかけた視点 『MeloMisterio』の美しい音色の余韻に浸りながら会場を歩いていると、まるで導かれるように次なる素敵な作品、『里山のおと 春さんぽ』と出会いました。プレイしてまず強く感じたのは、「もしかして、この川越 GAME DIGGというイベントのために作られたのでは?」と思えるほど、会場の雰囲気、そして当日のしっとりとした雨模様に、驚くほど自然に溶け込んでいたことです。大げさではなく、周りのブースからも「このゲーム、すごく雰囲気に合ってるよね」という会話が聞こえてきたほどだったので。 ジャンルはポイント&クリック形式のアドベンチャー。友達キツネくんからの「桜の下でお弁当を食べよう」という心温まる手紙を受け取ったタヌキくんが、目的の桜の木を探して冒険に出かけます。道中で出会う動物たちの助言や、道端で見かける植物を注意深く調べて得られる手がかりを頼りに、正しい道を探し当てて進んでいく…という内容です。どこか遠い昔の記憶を呼び覚ますようなストーリー展開と、水彩の筆遣いを思わせる温かみのあるアートデザイン。外は冷たい雨が降りしきっていましたが、ゲームの中だけは満開の桜がプレイヤーを優しく迎えてくれました。 絵本のような雰囲気ですが、抱いたのは「意外なほど、しっかり”ゲーム”としての手触りがある」という感想でした。私たちが普段想像する壮大な大冒険ではなくても、「友達に会いに行く」という、ささやかでミクロな冒険の中にだって、プレイヤーがゲームに期待する「試行錯誤する面白さ」や「発見の喜び」は十分に詰め込めるのだ、と深く感銘を受けただけです。 プレイヤーは手に持っている図鑑や、動物たちのアドバイスを元に、周囲の植物を注意深く観察することになります。そして、特定の植物の特徴を手がかりにして、目の前に現れる分かれ道のどちらがゴールの桜の木へと続いているのかを推理していく…。まるで小学生の頃の自由研究の課題のような、微笑ましくもちゃんと頭を使う探索体験に、気づけば短いプレイ時間ながらすっかり没頭していました。 こうした体験がなぜこれほど心に残るのか。それは、作り込まれた壮大な物語に没入する楽しさとは別に、こうしたミクロな視点から描かれる世界に触れることで、作り手が普段どんな眼差しで身の回りの自然や世界に触れているのか。その温かい視点の一部を追体験できるからではないでしょうか。正直、子供時代には持っていた、けれど知らず知らずのうちに失ってしまう感性や視点というものは、きっと少なくないはずです。このゲームは、そんな忘れかけていた何か…小さな発見に喜ぶ気持ちを、そっと掬い上げてくれるような、プレイヤーとしてはただただ有り難い時間を提供してくれました。 ところで、この素敵なゲームに私がたどり着いた経緯においても、少し面白いエピソードがあります。実は、『MeloMisterio』と同じ会場「コエトコ」の片隅、テーブルの上にふと置かれていた一枚のポストカードが、全ての始まりでした。白い紙に描かれた美しい桜の木のイラストに心が惹かれ、何気なく手に取ってみると、裏面には可愛らしい四コマ漫画が描かれていました。ゲームの大まかな導入部分がそこで紹介されており、「なんだこの可愛いゲームは」と感嘆し、そのままブースへと足を運んでしまったのです。この一枚は今後も特に大切にしまっておくつもりです。 そのポストカード同様、関連グッズも繊細で魅力的でした。特にブースで配布されていた栞のデザインはどれも秀逸で、思わず全種類を手に取ってしまったほど。ちなみにこの栞、投げ銭50円から、と案内がありましたが、とてもそんな価値ではいただけないと思い、勝手ながら一枚50円計算で4種類分、200円をお支払いさせていただきました。…と、ここまでは良かったのですが、なんとその際にお財布をブースに置き忘れるという大失態をやらかしちゃいました。もし、私の顔を制作者さんが覚えていなかったら、あの土砂降りの雨の中、東京から再び川越まで財布を取りに戻るという悲劇に見舞われるところでしたね。その節は本当にありがとうございました… インディーゲームには制作者さんの「好き」が色濃く反映されますが、時にプレイヤーを選ぶことも。本作も植物や動物への深い愛情を感じますが、その表現がユニークで温かいためか、普段馴染みのない人でも自然と惹きつけられる魅力があります。それはまるで、自分の専門分野について誰よりも楽しそうに、そして熱っぽく語る人の話に、テーマ自体への興味はそこそこでも、その熱意や人柄に惹かれて思わず聞き入ってしまう時の感覚に近いのかと。このゲームは、もしかしたら自分の中にも眠っているかもしれない、「道端の草花や小さな生き物を愛でる心」と久しぶりに再会させてくれた、貴重な体験となりました。 PONKOTS:予測不能な”ポンコツ”が生む、最高のカオスと協力の熱狂 さて、今回のレポートで紹介する最後のゲームであり、そしてこの雨の川越 GAME DIGGで、個人的に一番「面白い!」と感じ、そして一番大声で叫びながらプレイしたのが、この『PONKOTS』です。もう名前からして、ただならぬ「何か」が起こりそうな予感がしますね。 このゲームのコンセプトはすなわち、「互いに弱点をフォローし合う」ということ。3人から最大8人でプレイ可能な、協力型の2Dカジュアルアクションなのだそうです。世界観としては、プレイヤーは小さなオモチャたちを操作し、互いに助け合いながら、悪いブリキの王様たちから逃げて生き延びる…という、可愛らしい見た目とは裏腹に、どこか闇っぽさも感じさせるストーリーが背景にある様子。基本的なルールは意外とシンプルで、プレイヤーたちに向かって飛んでくる砲弾(ホウダン)に当たらないよう、ひたすら逃げ回るのが大前提です。 ただしここで強烈なひねりが。特定時間毎にランダムで一人、「ポンコツ」なり操作不能状態に陥ってしまうのです。他のプレイヤーは動けなくなった仲間がホウダンに当たらないよう、必死で押し出して位置をずらしたり、時には自らが盾になったりして守らなければなりません。刻一刻と状況が変わる中で、瞬時の判断力と仲間との呼吸が試されるのです。 説明だけではピンと来ないかもしれませんが、このゲームの面白さは体験しないと100%伝わらないタイプかなと。ただし私の体験では、イベント試遊で間違いなく一番声をあげていたゲームでした。もちろん、雨が降る屋外に近い会場で、多少大声を出しても大丈夫だったという前提条件が付きますが。 最低3人から、というのが少しネックで、一人参加の私は諦めかけましたが、制作者の方二人が快く加わってくださり即席プレイがスタート。初対面なのに、まるで旧知の友人の家に集まってスマブラでも始めるかのような、和気あいあいとした雰囲気の中で、簡単なゲーム説明を受け、気づけばオモチャたちを必死に操作していました。実際のプレイには更に多くの要素がありますが、確かなのは「息つく暇もないカオス」を連続的に演出し、皆が「うわー!」「そっち行った!」「助けてくれー!」と悲鳴にも似た歓声を上げながら、それでも笑いが止まらない、最高のパーティーゲーム体験だということ。もちろん、制作者さんの盛り上げも素晴らしかったです。 この面白みを例えると、常に「時限爆弾のタイマーが残り1秒で、赤か青か、正しい色のコードを切らなきゃ」的な状況が続いていることかなと。ポンコツ化、砲弾、ギミック等全てが予測不能な「ワチャワチャ感」のために計算されています。90年代風レトロアートやガチャガチャと鳴る金属質な効果音、焦燥感を煽るアップテンポなBGMも、切迫感を増幅させていました。そして体験の核が「ランダム性」の絶妙な使い方。多くの要素がランダムに決まることで、プレイヤーは常に不安定さと不確実性の中に置かれます。予期せぬ脅威にアドリブで対応するしかない。この「不安」が協力しなければという一体感を生み、最終的に「爆笑」へ昇華されるのです。このゲームをプレイして、「ああ、本当に面白い協力ゲームって、こういう熱狂を生み出すものだよな」と、改めてその理想形の一つに触れたような気がしました。 …と熱く語りましたが、少し個人的で突飛かもしれない考察を一つ(私の勝手な解釈です)。本作は、ある意味で現代における”アンチ・テーゼ”としてのゲームなのかも、と感じました。というのも、昨今のゲームは洗練されたソロ体験や個人のスキル重視が主流に感じますが、『PONKOTS』の協力はもっとプリミティブ。「ポンコツ」になった仲間を周りが文字通り体を張って必死で助ける、相互扶助そのものに重きを置いています。「個」の熟練度よりも「場」の一体感や、「みんな」でいることの偶発的な楽しさ、友達の家で騒ぐあの原風景こそが本作の核ではないか、と。 「ランダム性」の扱いも同様です。多くのゲームでランダム性は「便利な万能調味料」的に使われがちですが、『PONKOTS』では違う。プレイヤーを助けるのではなく、むしろ脅かし、カオスと協力せざるを得ない切迫感を生む「揺らぎ」として機能しているのです。だから悲鳴を上げつつ笑ってしまう。それは、子供の頃、友達みんなでトランポリンに乗って、不安定な足場にまともに立っていられずに転げ回りながらも、なぜかみんなで大笑いしていた、あの時の感覚にとても近いのかもしれません。 制作者さんとは深い話はできませんでしたが、何よりも、初対面の私に対して、あれほど熱心に、そしてご自身も最高に楽しんでプレイに付き合ってくださったことに、心から感謝の気持ちを伝えたいです。普通、協力プレイが前提のゲームを一人で試遊するのは物理的にも心理的にもハードルが高いことが多いですが、『PONKOTS』に関しては、「このゲーム、絶対に誰かと一緒に遊びたい!」という気持ちが、プレイ後、非常に強く込み上げてきました。これは本当に久しぶりの感覚です。まだ制作中のゲームとのことですが、「このゲームがリリースされる日までに、一緒に腹を抱えて笑い転げられる友達を、ちゃんと作っておかないと」 そんな、未来への妙な決意(?)と期待感まで抱かせてくれた、素晴らしい作品との最高の出会いでした。 雨の川越、ゲームとの一期一会 さて、ここまで雨天の中開催された川越 GAME DIGGで出会い、心を掴まれた4つの個性的なインディーゲーム、『湯斬忍者』、『MeloMisterio -play your melody-』、『里山のおと 春さんぽ』、そして『PONKOTS』について語ってきました。どれも、あの日の天気、あの場所でなければ、また少し違った印象を受けたかもしれない…そんな、まさに一期一会と呼ぶにふさわしい出会いだったように思います。 正直なところを言えば、イベントの大きな特徴であったはずの「オープンタウン型」というコンセプトは、残念ながら降り続いた雨によって、そのポテンシャルを最大限に体験するには少し難しい状況だったかもしれません。パンフレットを片手に、歴史ある川越の街並みを散策しながら点在するブースを巡る…という、当初思い描いていた理想的な楽しみ方は、叶わなかった部分も確かにあるでしょう。 しかし、だからといって、このイベントでの体験が無意味だったかと問われれば、答えは断じて「否」です。『湯斬忍者』が教えてくれた、ゲームを通じた地域コミュニティの熱意と新たな交流の可能性。『MeloMisterio』が響かせた、歴史的建造物というリアルな空間とデジタルアートが融合する、不思議なな音響体験。『里山のおと』がそっと気づかせてくれた、日常のすぐそばに潜む小さな冒険と、忘れかけていた優しい視点。そして『PONKOTS』が叩きつけてきた、協力プレイというものの原初的な熱狂と、笑いの絶えない最高のカオス。 これら一つ一つの強烈なゲーム体験は、たとえ悪天候という逆風の中であっても、いや、むしろそんな状況だったからこそ、より一層その輝きを増し、私の記憶に深く、そして鮮やかに刻まれたのかもしれません。それぞれのブースで、雨にも負けず、自らの「好き」と「作りたいもの」を形にし、訪れる私たちと情熱的に繋がろうとしていた開発者の方々の真摯な姿も、間違いなくその輝きを後押ししていました。結局のところ、どんな状況であろうとも、面白いゲーム、心を動かすゲームというのは、その本質的な魅力を決して失わないものなのだな、と改めて実感した次第です。 今回の川越